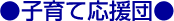
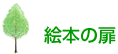
| 絵本を読む |
当たり前のことですが、一日中外で飛び回っている子どももいれば、いくら天気が良くても室内で静かに遊ぶことを好む子どももいます。子どもの興味の向かう方向は千差万別で、そのどれもが等価で大切です。子どもにとっては、絵本の楽しみもその中の一つに過ぎないのです。
絵本を子どもに読み聞かせることによって親子の関係が深まるとか、子どもの想像力をはじめさまざまな力が育っていくという話がよく聞かれます。それらは結果的には間違っていないと思います。しかし、私が子どもに絵本を読んで聞かせたいと思うのは、私が好きなもの、楽しいと思うことを子どもと共有したいという単純な思いからです。また、これはと思って読んだ絵本に対する子どもの反応が、自分の思いと違ってることも珍しいことではありません。しかし、それは子どものせいというわけではありませんし、絵本が悪いわけではありません。子どもと大人で感じ方が違うことなど住々にしてあることですし、それぞれの感じ方を大事にすればよいことだと思っています。ただ、絵風や言葉遣い、ましてや作者名などには全く先入観など持たず、目の前の絵本に真っ直ぐ向かい合っている子ども達の姿にはいつもかなわないと感じさせられます。 |
| 絵本の散歩道 |
| 多くの大人達にとって、絵本はもう通り過ぎてしまったものかも知れません。それでも子どもとの出会いなどをきっかけにして、また絵本と巡り逢うことがあります。それは、昔の懐かしい道をもう一度歩いてみるということだけではなく、今まで気が付かなかった気持ちのよい風景にであうことに似ているかも知れません。その時は、教育的な配慮などはちょっと横に置いて、自分が楽しいということを第一に考えてもそうバチは当たらないと思うのです。そのようなわけで、脇目もふらずに一生懸命ではなく、立ち止まったり、寄り道しながら楽しんでいけるようにと、とりあえず「絵本の散歩道」という名前でこのコーナーをスタートしてみようと思います。 |
| 絵本とは |
「絵本とは」なんて書くともうそれだけでこのコーナーの趣旨から外れてしまうのかも知れませんが、せっかくの機会なので、いろいろな方の絵本についての思いを少しずつ紹介していきたいと思います。
第一回は、今江祥智さんが『絵本の新世界』(大和書房、1984年第一刷発行)の中で述べている言葉です。「センダックの空想世界のみごとなひろがり、レオニの抽象手法の子どもへの応用、シュルヴィッツの映画的展開、モンディロのナンセンシカルな発想と遊びの精神、ほぼ一作ごとに大胆に画風をかえる長新太の冒険、言葉を極度にきりつめてすべてを絵で表現しようとする谷内こうたの世界、おたがいの立場を考える優しさを<思想>にまで高めた形で物語絵本で訴えるローベル…というふうに考えていくと、いまや絵本世界は、単に子どもたちのためにつくられたものではないことがわかる。
作家たちはだれもが、インタビューに答えて、絵本づくりはほかでもない、自分のためだと、異口同音に述べている。自己検証のため、自分の愉しみのため、自分の裡なる子どもとの対話のため−と、表現はちがうが姿勢は同じである。絵本は、大人から子どもへ贈られる初めての<本>である。絵によるメッセージである。未知の世界への扉を開いてくれる不思議の国への案内人である。
子どもたちは、そこを通ってさまざまな世界へ出ていき、遊び愉しみかんがえさせられよう。だが、すぐれた絵本の読者は、子どもだけではない。絵本の世界のひろがりだけ、読者の上限もまたひろがっている−というのが現状である。かつて大人が子どものための本を書くことを考えようともしなかった時期に、子どもたちは自分たちの読物を大人の本箱から探してきた−というアザールの指摘は、いまでは逆になってきている(中略)
絵本は開かれた新しい世界を提示する、子どもが人生で初めて出会う<本>である。子どもの美意識づくりに、知らず知らずのうちに参与している<絵>である。日本語の文章と初めて出会う<読本>である。さまざまな遊びとはちがった、独自の愉しみを知らせてくれる劇場である。100人の子どもがいれば100ある個性の、いちいちとつきあう多様な世界をもち、それこそ3歳から80歳までの<人間のための本>なのである。」
ほんの一部分しか紹介できませんが、是非ご一読をお勧めいたします。 |
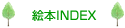
|

