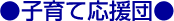


 |
平成18年1月28日(土)第43回横浜市幼稚園教育研究大会、第45回神奈川県私立幼稚園教育研究横浜地区大会が、神奈川県民ホールにおいて開催されました。午前の全体会ては来賓の
中田市長からご挨拶をいただいた後、「幼稚園における子育て支援を考える」関わりの難しい子はなぜ増えてきているのか〜乳幼児精神保健臨床の現場から見えてくる親子関係の変化〜というテーマで、慶應義塾大学医学部小児科学教室専任講師の渡辺 久子先生をお招きし講演していただききました。
「私たちの仕事は、クリスタルガラス、それもとても高級なのコップを粉々にした破片を、ひとつひとつ積み重ねて元に戻していくような仕事です」
この言葉を聞いたのは小児精神保健の専門家である渡辺久子先生が講演前講師控え室で話された言葉です。拒食症になった少女が、もう動かすこともできず、ただ点滴だけで生き延びている瀕死の状態で、その子をいかに普通の子どもに戻していくことが困難かを上記のように表現されたのです。この子は拒食症になる前は、素直でいい子で、成績もオール5に近く、親も高学歴という子です。そのような子が偽りの自分を作ろうと、「いい子でいたい」「きれいでいたい」という思いから拒食症になっていくというのです。
いま、渡辺先生の実感では、このような子ども達がすざましい勢いで増えてきているといいます。講演の中でも渡辺先生が触れられましたが、乳幼児の時から、親に信頼されているという安心感がなく、「目を合わせない」、「凍り付く」、「闘う」、「ゆがめる」、「大人することの逆をする」といった子どもが多くいるといいます。子どもはハッピーと感じるときにに成長することを強調される渡辺先生の言葉に、裏返せば、乳幼児の時代に安心感を感じられない子どもが増えている実態があること、そのために幼稚園にもかかわりの難しい子が増えてきているという流れが見えてきたのです。 ただし、ではこの原因を「親が悪い」という一言で済ませていいのでしょうか。子育てがうまくいかないのは、すべて親のせいとしてしまえば、幼稚園の保育を見直す必要はありません。親が悪いだけでなく、子育てがしにくくなっている社会の問題でもあるとするならば、幼稚園の果たすべき役割も見直してみる必要があります。そのことを、渡辺先生はヒラリークリントンの言葉を引用して、「一人の子を育てるには、一つの村が必要である」という言葉で表現しました。
地域や社会の中で子どもが育っていくという、一昔前では当たり前だったことが崩れ去り、個々の親に親の責任として「ちゃんと育てなくては」という過度のプレッシャーを与えているのです。幼稚園でもつい発してしまう「あの子は・・・」「あの母は・・・」といった言葉が、どれだけ現代の母子関係をゆがめているかもわかりません。まずは一人で子育てを背負い苦しんでいる母親を救うことが子どもの救済にもつながっていきます。できれば父親の育児参加を促すことも重要な幼稚園の役割といっていいのではないでしょうか。
大人の意図に合わせるだけのいい子を育てるのではなく、子どもの心の根っこの土壌を耕すことに、幼稚園がもっと力をいれて考えてみる必要があります。そのためには、乳児期も含め、親子関係にも視野にいれ、子どもの育ってきた環境や、今の保育のありようを見直すことが求められています。
少子化対策が叫ばれている今、何が子どもに起こっているのか、そして何が子育てを難しくしているか、子育てが難しくなっている中で幼稚園または現場の保育者は何ができるのか等々、保育についていろいろな示唆を与えてくれる貴重な機会となった講演となりました。 続いて午後の分科会では、横浜市幼稚園協会の教育研究部が行っている3つの特別研究委員会と、横浜市内で行っている区単位の研究から、神奈川支部、保土ヶ谷支部、金沢支部、青葉支部、栄支部、泉支部、計6支部がそれぞれ研究成果を発表し、各分科会に参加した保育者間で活発な討議を行いました。終日にわたり幼児教育の研究発表、話し合いを行いました。 |
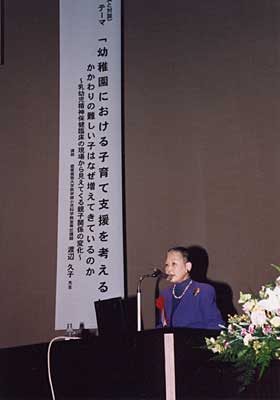
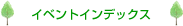
|

