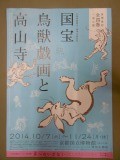10月2014
ききょう塾の子どもたちが志津川の陶芸教室に行った日のこと。こちらは、室内に閉じこもり、ある保育園の運動会のビデオを見ていました。内容的には、少し、おもしろいものもありました。
太陽が丘の球技場で行われていましたが、自分としては、保育園はどちらかと言えば、自由保育的なイメージを持つのですが、この園は、自由保育を標榜しながら、設定保育的なところが多々ありました。
一般的と言えば、現在と違い、昔の保育園は収容人数が少なかったので楕円形のトラックを描くよりは、(2本程度)直線を引いたグラウンドで行われることが多いようです。
年長児は竹馬や自転車に乗り、1メートル20センチほどの高さの巧枝台から飛び降りるというサーキット的な演技が目をひきました。いずれも、この運動会を目指して取り組まれていたようで、自転車などは、からだは左右に揺れながらも、全員がどうにか乗れるという第一段階はクリアされていたのが印象的でした。また、自転車の数とヘルメットの数にも驚きました。
先生方はなかなかの肉体派でした。2・3歳児が寝転んでいる先生の背中の上を転がったり、歩いたり。スキンシップは取れているのでしょうか・・・なかなか大変だなぁと思いました。
グラウンドにシンセサイザーを持ち込み、生の音楽で演奏するところなど、見習ってもよいかなと思うところもありました。また、プログラムの最後の方には、全員が球技場の周りを走るマラソン(618メートル)がありましたが、走る距離を明確に把握されているのにも感心しました。
また、ビデオを見ていて連想したことは、広野幼稚園が行っている年中児の玉入れと大玉転がし(ハンカチ落とし)をドッキングしてみる年があってもいいのではないかと思ったのでした。
2014/10/14 1:34 AM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:自称、保育バカ
3連休の最終日、台風第19号が日本列島を縦断するということでした。朝からテレビを見ていますと、JR西日本の全線が午後4時から運休するとのことです。
そこで考えました。京都の国立博物館の明治古都館で開催されている“国宝鳥獣戯画と高山寺”展は、大阪や神戸から来る人は少ないからてっきりすいているであろう、それなら、開館されるや否やすぐに入ってしまえば、今日の雨風は関係ないのでじっくり見られるかもと予測したのでした。
そこで準備万端整えてと、入場券を購入する時間を節約しようと、セブンイレブンで前売り券を購入し、平日はめったに乗らない車を運転し、ぎりぎり駐車場に入れる時間を想定し、8時50分に家を出たのでした。
開館までは15分、順調に車を走らせましたが、博物館の門前は9時30分の開門を待つ人達で長蛇の列、それでも、駐車場さえ空いていればと思いましたが、はや、満車の標識、“しまった”と思いましたが後の祭りです。朝からの綿密な計画はすべておじゃんになってしまいました。
それにしても、あれだけ、台風が来ると言われているのにとの思いもしきりです。避難勧告や避難指示がでてもなかなか避難する人が少ないことは聞いていますが、今日の自分のように考える人が多ければ、納得できることでした。
あっさり、予定を変更し、帰途についたのですが、その途中、烏丸通りから下立売通りに入ると、平安女学院高校の平成14年4月より幼児教育コース新設の垂れ幕が、改めてはっきり目に飛び込んできたのでした。
近ごろ、多くの保育施設が新しく開園し、保育者不足が云々されていますが、この職業に関心を持つ方が、早くから専門職としての心備えや技術を習得していただけることは非常にありがたいし良いことだなぁと思いながら、通り過ぎました。
2014/10/14 12:11 AM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:園長
台風19号が近づいてきていますが、今日はお陰さまで穏やかな秋晴れでした。
ききょう秋の遠足は毎年恒例の“陶芸にチャレンジ”です。
今年は志津川陶芸教室さまにお世話になりました。
陶芸に勤しむ前には、田辺公園に寄り、アスレチックで一汗かきました。今回初めてそこが花見山公園という素敵な名前であったことを知り、次の桜の頃にはぜひ訪れたいと思いました。

お弁当を食べているときのみんなの幸せそうな顔を見ていると、こちらまで幸せな気持ちになれます。
かわいいおいしそうなお弁当に、お母さまの愛情を感じました。



その時、突然ヘリコプターが10機公園の上空を飛び去って行きました。

「あ!御嶽山に救助に行かはるんかな」と即座に出るのもさすが小学生です。
そして、いよいよ芸術の秋、陶芸です。

ろくろの上の粘土と向き合い悪戦苦闘した結果…


ジャーン!!

これは誰の作品でしょう?
これから乾燥させて、焼いて、色付けをしてまた焼いて…と1ヶ月程かけて完成させてくださいます。
志津川陶芸教室の皆さま、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
11月22日・23日に行われる、広野幼稚園の作品展に展示しますので、どうぞお楽しみに。
2014/10/11 5:02 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:乗り気コラム
“灯台、元、暗し”という言葉がありますが、まさにこの言葉どおりで、保育上の一つのノウハウが見つかりました。その灯台とは、広野保育所です。お粗末なことに、これに隣接している広野幼稚園は、この事実にまったく気づかないでいたのでした。その事実とは、運動会の演技種目の一つ、日本中の幼稚園・保育園で行われている“かけっこ”のスタートに関するものでした。
ある日、室内運動会を控えた保育所の乳児組が、広野幼稚園の講堂でリズムやかけっこの練習をしていました。この活動を舞台上で原稿の校正をしながら見るともなく見ていますと、“あっ”と驚いたことは、2歳児のスタートについてでありました。
それは、スタートテープを持っている二人の保育者が少しずつ後ろへ下がっていっているのです。後ろへ下がると言いますと、テープの持ち手と持ち手の幅が広がるとも受け取れますが、そうではなく、スタートテープの長さは同じで、保育者がそのテープを子ども側に近づけていくのです。
最初は、スタートテープを前にして4人ずつ走る子どもが8列並んでいました。ここで、日本各地で行われている方法を書きますと、第一走者がスタートした後は、第二走者がスタートテープのほうに近づきます。なぜなら、スタート位置は変わらないからです。この状態をより深く説明しますと、保育者が決めたスタートラインに子どもが近づくということになります。
ところが、実際に行われていたのは、子どもたちは4人並んだまま一歩も動かず、保育者の持つテープ(スタートライン)が子どものほうに近づいていたのです。イメージできましたでしょうか。
“な~るほど”と感心せざるをえません。このような子ども本位な事柄を多く集め、実行していくことが、子どもたちに寄り添った保育と言えるのではないでしょうか。
広野幼稚園の来年度の運動会では、早速、満3歳児がこの動きを取り入れたいと考えています。
2014/10/10 5:00 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:自称、保育バカ
上端部をわずかに残したお月さまを見ながら“そうだ、東へ向かって歩こう”と心に決めました。東へ向かうということは、この間ずっと月を眺めていることができるからです。
京都駅を後に、右には新幹線、左側には在来線が見える鉄道警察会館の西側のスペースに腰を下ろし、変化する月と、時を同じくします。京都駅のほん近くながら、道行く人はあまりありません。
上端部にわずかな光を残すだけになった頃には、再び歩きだしました。昔々、はやった“月がとっても青いから、遠回りして帰ろ”の歌が飛び出しますが、現実の月は赤銅色です。私にとっては、とても美しいとは表現しづらい色でした。
何本も通る在来線の上を通り、塩小路通りの手前にあるラーメン店、第一旭は20人ほどの行列でした。知る人ぞ知る人気店なのでしょうか。この中で月を眺めている方はおられないようでした。あまり、食には関心がありませんので、さっさと横を通り過ぎます。
鴨川まで来ると、東山連峰の上からかなり離れたところに月が見えます。通り過ぎる涼しい風に本格的な秋を感じながら、しばしの風流を楽しみます。
三十三間堂の裏側を通り、東大路へ向かいます。蛍光灯が明るい外灯の近くでは月はその姿を隠しますが、すぐまた、現れます。現在、京都は観光ブームですごい数の方々に来ていただいていますが、月を見ながら歩く観光をなさる方は少ないのではないでしょうか。このようなことができるのは、地元に住む人間のありがたさです。
東大路まで来ますと、京都国立博物館がもうすぐです。ここでは、平成知新館という名称の新館が、この9月に新装開店(?)しました。また、この7日からは、京都は北の高山寺の寺宝というよりも、日本の得難い絵巻物“鳥獣戯画”の全四巻が展示されています。子どもたちでも興味が持てる絵ですので、ご関心をお持ちの方はぜひお出掛けください。
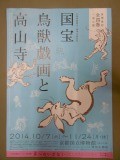
皆既状態の月はしばらく変化しそうにないので、202番のバスに乗りました。
2014/10/10 3:57 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:自称、保育バカ
« 古い記事
新しい記事 »