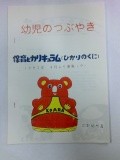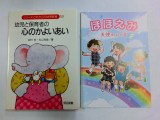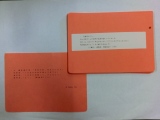9月2014
運動会を半月後に控え、子どもたちの練習も室内で動きを覚える段階から、園庭やサッカーグラウンドなどで隊形移動を交えた練習に進みました。今年の9月は、近年の9月よりも少し涼しく感じられますが、練習をさせられている子どもたちはどう感じているのでしょうか。
私たちの幼稚園には、いろいろな音響機材がありますが、それが有効に使われているかどうか、なかなか評価は微妙です。本日の太陽ヶ丘での予行練習に先立って昨日、講堂で根本的見直しを行いました。
昨日までの予行練習では、小さなアンプに1個だけのスピーカーを持参するだけでした。それは、予行練習だから簡単な機材でという訳ではなく、20数年前からこういう態勢で行っているからという理由で続けていたのでした。日進月歩の社会でなくても、これでは時代からドロップアウトします。
そこで、古い頭脳に破壊的刺激を与え、運動会当日とほぼ同じ音響設備を整えてやってみようではないかということになりました。予行練習にはすべての機材や子どもたちが使う運動具を一台の軽トラックに乗せて太陽ヶ丘まで運ぶのですから、できるだけ音響機材は少なくし、運動具を多く乗せたいのが保育者の本音でしょう。
ところが、今日の予行はこれに反する設定なので、近視眼的に見れば、子ども中心でないのではないかということも言えないことはありません。その反対の意見として、ダンス系の音楽がはっきりと子どもたちの耳に届くということも、環境設定上の大きな改革・進歩ではないかと思っています。
合わせて、去年度はプロの音響屋さんに入っていただきご指導を受けましたので、今年から予備の電源を持参するようにいたしました。本番当日の不慮の出来事に備えるという意味で、小さな進歩ではないかと思っています。
2014/09/19 4:09 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:自称、保育バカ
「楽しかった!」「汗いっぱいかいたわ~!」と、運動会の練習を楽しく取り組む声が聞こえる毎日です。
今日は、異年齢交流として、年中組と年少組で一緒に昼食をいただきました!
年中の子どもたちも、少しすまし顔で「おじゃまします」としっかり挨拶してくれ、年少の子どもたちも初めてのお兄さん、お姉さんにドキドキしている様子。。。
しかし、大好きなお弁当を開けると「あ、同じおかずが入ってる!」と、年中の子どもたちから声を掛けてくれ、食べ終わる頃にはあっという間に仲良しになっていました。

お昼の自由遊びでも、一緒に遊んでくれたお兄さん、お姉さんもいました♪
「また一緒に食べようね!」と約束していた子どもたち、次回の異年齢交流も楽しみですね!
2014/09/18 7:25 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:くまのこジャッキー
本日、午前10時に宇治市の市会議員の一人である鳥居氏の紹介で、宇治市の石田教育長にギネスへ登録しようとしている子どもの言葉や子どもの行動について、広野幼稚園の長年に渡る取り組みを簡単に説明させていただきました。
持参した書類は、平成の始めごろ“ひかりのくに”から出版されている、幼児教育雑誌“保育とカリキュラム”の表紙裏を1年間に渡って飾ったものの冊子、自費出版の単行本“風の詩”シリーズのうちの2冊、これらから導き出された子どもの思いをまとめた明治出版から出していただいた単行本“幼児と保育者の心のかよいあい”、この3月に京都マンガミュージアムのご協力で視覚に訴えた“ほほえみー天使のひと言ー”の4点だけでした。
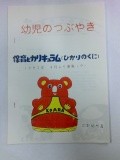

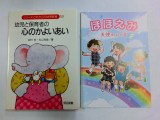
この他、ギネスへの登録を目指しての話では、今後の作業内容がイメージできるようにと、(風の詩241を解体切断した)一会話・一行動を一枚ずつの台紙に貼ったアナログ的な241枚の束、それと合わせて、今後の作業で活用するパソコンを駆使し、直接台紙にプリントした1枚をお見せしたのでした。ご感想は、「やはり手作り感のある方が・・・」とおっしゃっていました。
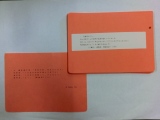
懇談中、常に書物から目を離さず、それでいて私のつたない説明に耳を傾け、大体のアウトラインを読み取り、ギネスへの登録を目指す意義を十分に理解していただきました。無言のバックアップを得たようで心強く思いました。
実質は20分足らずでしたが、お互いの意志の疎通ができてうれしかったです。仲介の労をとっていただきました鳥居議員様、どうもありがとうございました。
2014/09/18 5:22 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:園長
昨日の“保育バカ”さんのブログを読んでいて、「あ!」と思ったことがありました。
危険個所に気づいたら一つひとつ改善して安全な環境作りを目指している広野幼稚園ですが、それを保護者の方に伝えなければ、いつまでも危険なのかしら…?と心配されるのではないかということです。
夏休みの終わりごろに、せせらぎにはまって池ポチャ…という内容の記事がありましたが、実はその方が池ポチャされる10日ほど前に、私も同じ個所で池ポチャしていたのです。。。台風がくる準備をしていて、全く同じシチュエーションでポチャッ。
そのことを、園長先生に伝えると、次の日には早速、運転士さんに依頼してくださり、竹製の日本風柵が出来あがっていました!仕事が早い!
「これでmaikkaさんも、もう落ちませんね」と冗談交じりにおっしゃっていましたが、私以上に、2学期以降の子どもたちを心配されてのことなのは言うまでもがなです。
これで安心~と思っていましたが、そのままで終わっていては、保護者の方には伝わっていなかったなと気づいたのです。
遅ればせながら、趣ある柵をご紹介しておきますね。

2014/09/17 6:53 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:Maikka
敬老の日、長岡京市のむらさき幼稚園の家田光信先生の瑞光単光章の受賞を祝う会が、京都は蹴上のグランビア京都で行われました。広野の初代の通園バスの絵は、光信先生のお兄さんの故隆現先生に描いていただいておりますので、何はともあれ、お祝いにと出向きました。
まずびっくりしたのは、記念誌として発行されたタイトル名“敬老慈幼”の内容の一部でした。これは毎月むらさき幼稚園が発行されている、いわゆる、お知らせの中の園長言をまとめられたものではありましたが、この中のコラムとして、“幼児言行録”という欄があったのでした。ほっと一息してくださいということなのでしょう。私たちの幼稚園のお知らせの中には“ほほえみ”という見開き2ページが存在しますが、それと同様の主旨です。同じような試みをなさっている園が近くにあるということ、我が意を得たりという感でした。
広野幼稚園では、過去30年間に渡り、子どもたちの言葉や行動を集め、その数5000以上と思っていますが、まだまだ、子どもたちの奥底をのぞくまでには至っていません。このような同志の幼稚園が一つでも多くあることは心強く、今後も多くの方々のお力を借りながら、より数多く集め、少しでも子どもたちの要求がくみ取れる幼稚園を目指して行きたいと思っています。
何日か前に書きましたギネスへの登録の件、楽しみながら少しずつ進めております。あせらず・気長に・ゆったりとをモットーにしています。保護者の皆様も楽しみにお待ちください。
追伸 最後にお笑い草を。会が終わった後、市バスで乗ったのですが、ついうとうとしてしまい、京都市内をほぼ半周してしまいました。バス停を一駅ぐらい、乗り越したかと飛び降りたところ、10個も過ぎていたのには驚くとともに、びっくり、がっくりしました。
タクシーで帰るべきだったかな?
2014/09/17 3:19 PM |
カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |
投稿者名:園長
« 古い記事
新しい記事 »